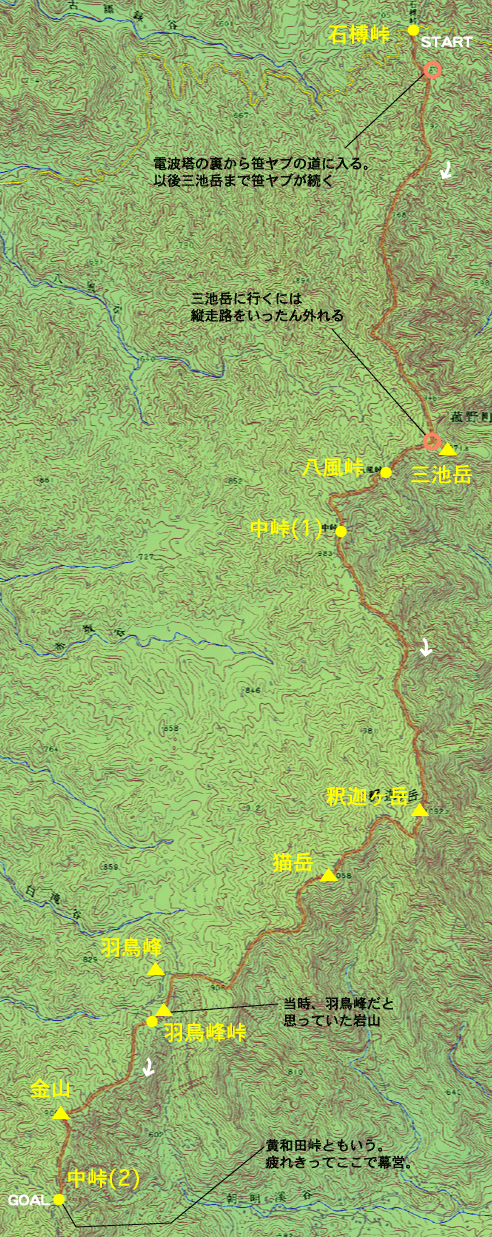鈴鹿縦走路のほぼ中間地点に位置する釈迦ヶ岳は、
鈴鹿スペシャルの中でも屈指の難所です。この山を含む区間は滋賀県側からのアクセスが最高に悪く、日帰りで登って降りてこられるような登山口が一つもありません。踏破するには、北の石榑峠から南の武平峠に至るまでの、ざっと17km(水平距離)におよぶ長大な稜線を、2日間かけて延々歩くしかないのです。滋賀県以西のハイカーに
「陸の孤島」「奥地の恋人」などと言われるゆえんです。我々以外誰も言ってないかもしれんけど。
ここでしじみとMの大いなる足かせとなったのが、鈴鹿スペシャルの唯一の掟である
「三重県に降りてはいけない」という制約。釈迦ヶ岳の南のふもとに位置する
朝明キャンプ場を泊地・補給地にするのがこのルートの最も妥当な歩き方なのですが、掟に従って我々はそれを蹴り、山中のテント泊を選んだのです。しかも滋賀県側の水場を使う関係で、わざわざ登りの多い南下コースに挑戦。別に
三重県に何か恨みがあるわけでもないのに、妙な片意地張らなきゃよかったなあ・・。
決行前日にあらかじめ武平峠に車を配し、翌日もう一台の車で石榑峠へ。あいにくのどんより曇った空の下、電波塔の裏手から出発です。石榑峠〜三池岳間は行く人も少ないのでしょう、笹ヤブに埋もれて消えかかっている道を、かきわけかきわけがむしゃらに進みます。


夜露たっぷりでツユダクの笹の洗礼を浴び、すっかりビショビショの我々。
ちなみにMが両手をあげているのは、濡れ具合を見やすくしてくれたそうです。
でも写真にするとあんまり分からない( ^-^;)なんか投降ゲリラ兵みたい。
2時間ほどかけて笹ヤブを抜け、三池岳への分岐に出ました。ここは少しひらけています。しかしすごい濃霧で、残念ながら眺望は全くありません。

ウチのサイトの写真ってこんなんばっかだな。
ここで、稜線を北上してきた単独行のおじさんに出会いました。三國連太郎に似たカッコイイおじさんで、ビショビショの我々をいぶかりもせず、親切にコーヒーをわかしてふるまってくれました。しじみもお返しにおやつのゼリーでもあげようかと思ったのですが、この先の遠大な行程を考えるとゼリー1つといえどもムダにするわけにはいかず、何ももってないフリをしました。人として最低ですね。
おじさんと別れ、昼食をとり、三池岳に寄りました。残念ながら林に囲まれて眺望はありませんでした。縦走路に引き返し、先を急ぎます。程なくして八風峠に到着。ここにはかつて神社があったらしく、小さな鳥居と、「八風大明神」の石碑があります。

八風大明神の碑
「おおお、ヤフー大明神だ!」
「ここにお参りすればソフトバンクホークスも優勝間違いなしだぜ!!」
(注1・当時はまだ7月でした)
(注2・ほんとは「はっぷう大明神」です)
別に二人ともホークスファンでも何でもないんですが、何だかこれで奇妙に盛り上がり、中峠を越えて、釈迦ヶ岳までの長い長い尾根道をオタクネタをくっちゃべりながらズンズン進みました。でも実際のところは、ハイになることで、徐々に感じはじめていた疲れから気をそらしていただけなんですが・・。
そしてたどり着いた釈迦ヶ岳は、残念ながらこれまた霧のせいで眺望皆無。あこがれていた奥地の恋人(←しつこい)は少々期待はずれでした。
(※この時は知らなかったのですが、晴れていれば三重市街がよく見える良いピークです)
「これのどこらへんが『釈迦』なのかねえ」
「むしろ『おしゃか』だねえ」
先ほどの八風大明神といい、不敬なことを言いまくりです。
疲れているせいです許してください( ^-^;)
この時点でもう15:00。先を急がねばなりません。
猫岳を越え、羽鳥峰(はとみね)に向かいます。羽鳥峰とハト胸をかけたギャグを言いたかったのですが、疲れてて無理でした。いや疲れてなくても無理だと思う。
羽鳥峰峠一帯は風化した砂礫地帯で、茜色の夕陽を浴びた白砂の丘陵が何とも幻想的できれいでした。八風大明神の呪いか、いきなりデジカメの電池が切れて写真が撮れなかったのが心残りです。
(※当時、しじみたちはコース上の名もない岩山を羽鳥峰と思っていましたが、それは間違いで、縦走路は羽鳥峰を通らないことが後に判明しました。詳しくは羽鳥峰登山録をご覧ください)
そして、続く金山の急登でついに二人とも疲労が限界に。金山頂上(ここも展望なし)でどちらからともなく「もうどこでもいいから適当なところで幕営しよう」と言い出しました。すでに17:30、日没を考えても、もうこれ以上は危険です。そこで下りきった中峠(黄和田峠とも。このコースは「中峠」が2つあってややこしいです・・)でついに荷を降ろしました。峠の隅にテントを立て、服を着替えてバタンキュー(死語)です。
予定の水場までたどり着けなかったので、食事は手持ちの水だけで何とかしのがなければなりません。二人とも、日中の行程ですでに各2リットルを消費していました(プラティパスは残量が見えないため、ついつい飲み過ぎてしまうのが欠点です)。残りは二人あわせて3リットル。このためあえなく、楽しみにしていた夕食のカレーを断念しました。水を使い過ぎてしまうからです。
酒のつまみとなるはずだったウィンナーを炒めて主食とし、カレーのデザートとなるはずだった袋詰めパイナップルをおかずとするわびしい夕食をとって(パイナップルのシロップは壮絶なるジャンケンの末Mが飲んだ)、足りない分はカロリーメイトをかじって空腹を埋めました。水なしで食べるカロリーメイトは拷問に等しいということを学びました。
食べ終わってもまだ7時頃でしたが、何もすることがないしする気力もないので、寝ることにしました。ところがそこは鈴鹿の山、そう簡単には寝かせてくれませんでした・・(続く)
釈迦ヶ岳・御在所山(後編)へ